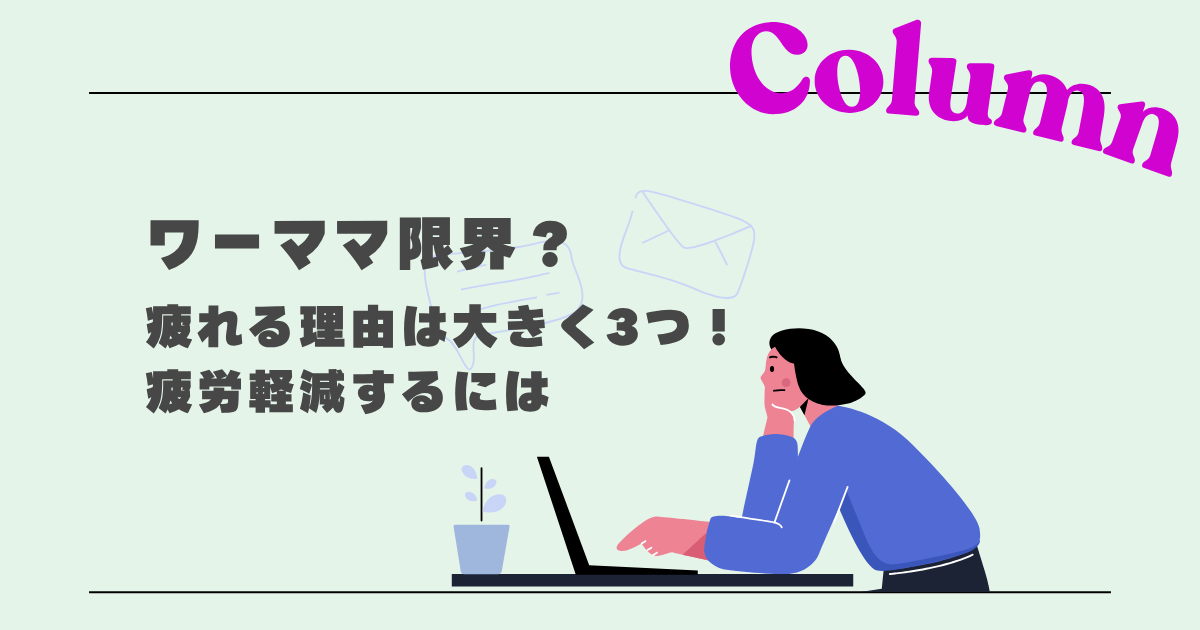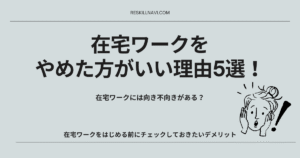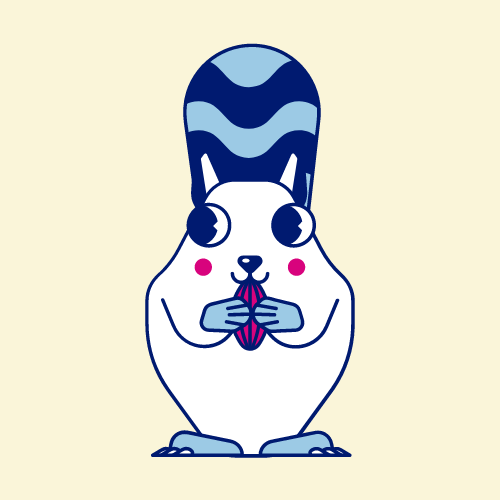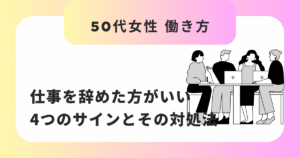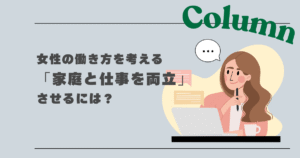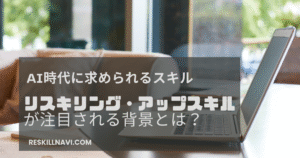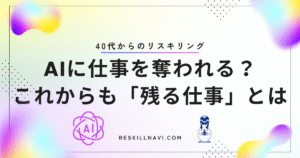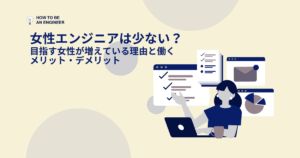ワーママに限界を感じて、「疲れた」「もう無理」と思っている人は少なくありません。
家庭と仕事の両立は、子育て中のママにとっては常に悩ましいテーマ。
朝の朝食作りから始まり、子供の支度、自分の出勤準備。仕事を終えて帰宅すると夕食の支度や洗濯、翌日の準備が待っています。
一日中フル稼働で動き続け、「この生活、いつまで続くんだろう…」と感じてしまうのも無理はありません。
仕事と家庭の両立が難しいのは、ママの頑張りが足りないのではなく、時間、心、環境の3つの側面で無理を強いられているからです。
この記事では、ワーママが疲れやすい理由を3つの視点から整理し、今日から少しでもラクになるためのヒントを紹介します。
- ワーママが疲れる理由を3つの視点から
- 時間的疲労を軽くする具体的な方法
- 精神的疲労を軽くする具体的な方法
- 環境による構造的な疲労を軽くする具体的な方法
ワーママはなぜ疲れる?その理由を3つの視点から考える
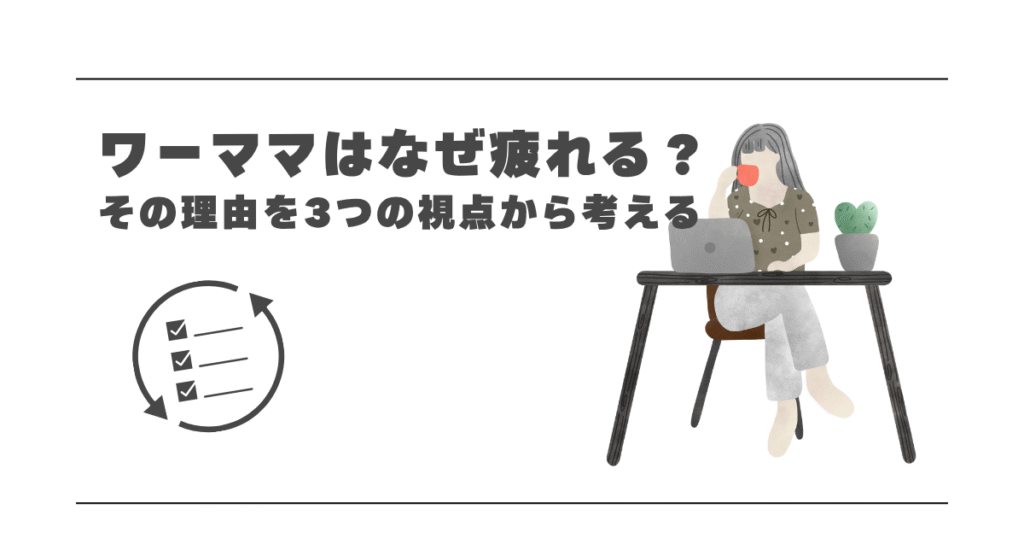
ワーママはなぜ疲れる?その理由は大きく3つあります。
- 時間的疲労
- 精神的疲労
- 環境による疲労
順番にくわしく見ていきましょう。
時間的疲労
時間の余裕のなさは疲労の大きな原因です。
- 物理的に時間が足りない
- 仕事で疲れた状態で急いで次の仕事にいくような状態
- 自分の自由な時間がない
- 頭の中はスケジュール管理でいっぱい
ワーママが疲れる理由には、物理的に時間が足りないことが大きな理由として挙げられます。ワーママの一日はフル稼働で、一つの仕事を終えたあと、すぐにもう一つの仕事が始まるようなもの。

ホッと一息つく間も無く、頭の中はこの後のスケジュール管理でいっぱいの状態になりがち。
自分の自由な時間を確保したくても、1日の中に組み込む余裕もありません。
このような状態が毎日続くと、どれほど元気な人であっても「疲れた」と限界を感じるのも無理ないですね。
精神的疲労
次に精神的疲労もワーママが疲れる要因です。
つい、あれもこれも自分のタスクと捉えて、やってしまおうとする人は限界を感じやすくなります。



とくに、完璧を求め過ぎてしまう人は、精神的な疲労が大きくなりやすい。
育児や介護をしていると予定通りに進まないことは日常茶飯事。わかってはいるものの、突発的な予定変更には大きなストレスが伴います。
一日中フル稼働で体力的に疲れているところに、メンタルまで消耗してしまうなんて…ワーママには心の余裕が必要です。
環境による構造的疲労
家庭や職場環境の構造による疲労は、ワーママの時間的疲労や精神的疲労につながる根っこの原因となっています。
家族や職場の協力なしには、家庭と仕事の両立は成り立ちません。困ったときにサポートしてくれる職場の理解であったり、夫や両親の協力が得られたりといった安心感は精神的疲労を和らげるのに不可欠です。
環境による疲労を解消することが、時間的な余裕や精神的なゆとりを生み出すことにつながっています。
時間的疲労を軽くする具体的な方法
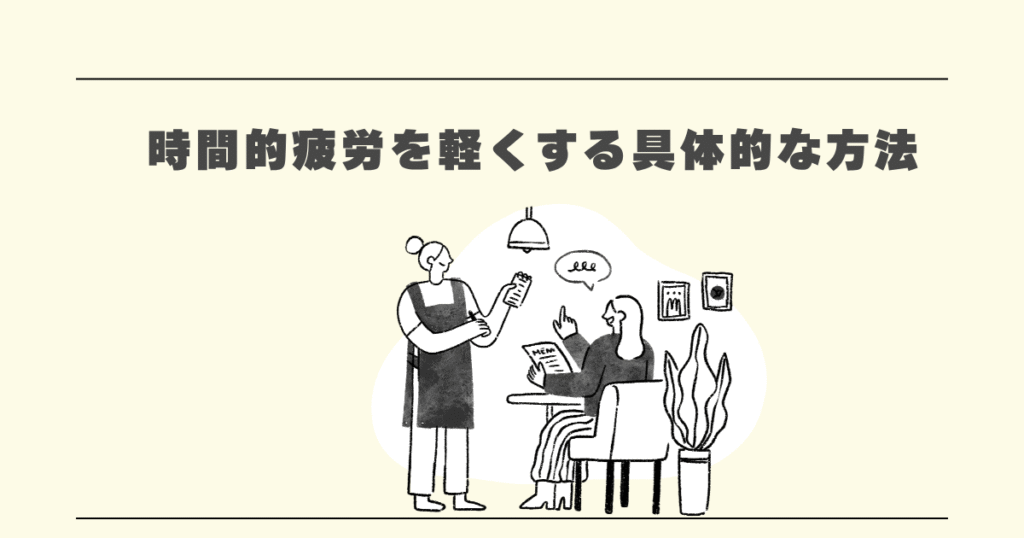
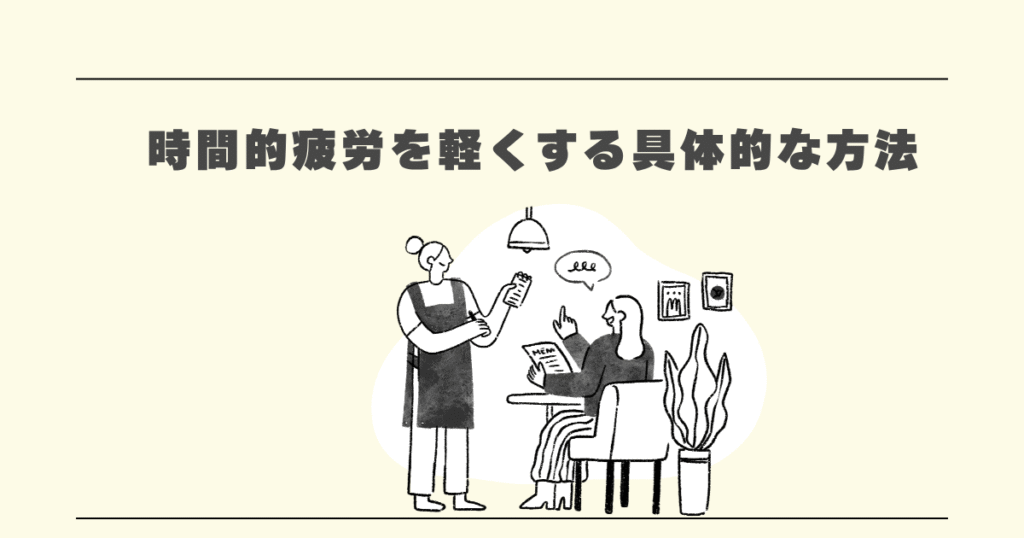
ここからは、疲れを軽くするための具体的な対策方法を紹介します。
- 完璧主義をやめる
- 家族の予定を「見える化」脳の負担を減らす
- 頼れる人・サービスをリストアップ
- 何もしない時間をスケジュールに組み込む
時間的疲労を軽減するには「脱完璧主義」
時間的疲労を軽減するには、完璧主義をやめることです。
ワーママさんの中には、仕事も家庭も中途半端にしたくないという気持ちから、ついがんばり過ぎてしまう人も多いのではないでしょうか。
家族全員のスケジュール管理を担うワーママにとっては、予定通りに進まないことがストレスの原因の一つとなります。
突発的な予定に対しては、
- 頼れる人を確保する
- 事前に相談し職場の理解を得ておく
ことが大切です。
家事・育児のタスクを「見える化」
頭の中でスケジュールを管理していると、「次に何をするんだっけ?」と考えてしまい、脳が休まる時間がありません。
家族共有のスケジュールを管理するカレンダーアプリ「Googleカレンダー」「TimeTree」を使用したり、ホワイトボードに予定を書き出したりするなど。



タスクの「見える化」が時間削減のカギ
やらない家事を決める、サービスに頼る
すべてを自分でこなそうとせずに、やらない家事を決めてしまうことも効果的です。
自分がしなくても困らない家事は、家族の誰かにお願いしたり、外部サービスに頼るといった工夫をしましょう。
たとえば、
- 食事は惣菜や宅食サービスを活用する
- 掃除機はロボットにお任せ
- 週に1回家事代行サービスを利用する
など、自分の時間を確保するために意識的に人に(機械に)頼る工夫が必要です。
何もしない時間をスケジュール化
何もしない余白時間を30分〜1時間スケジュールに組み込んでおきましょう。
自分の趣味の時間として確保し、たとえ他のタスクが気になったとしても、その時間はなるべく自分のために使うように意識します。
メリハリをつけることで、次の行動のエネルギーになり、1日を振り返ったときに「あれができた」という充実感にもつながります。
精神的疲労を軽減するには「ゆるめる時間」の確保
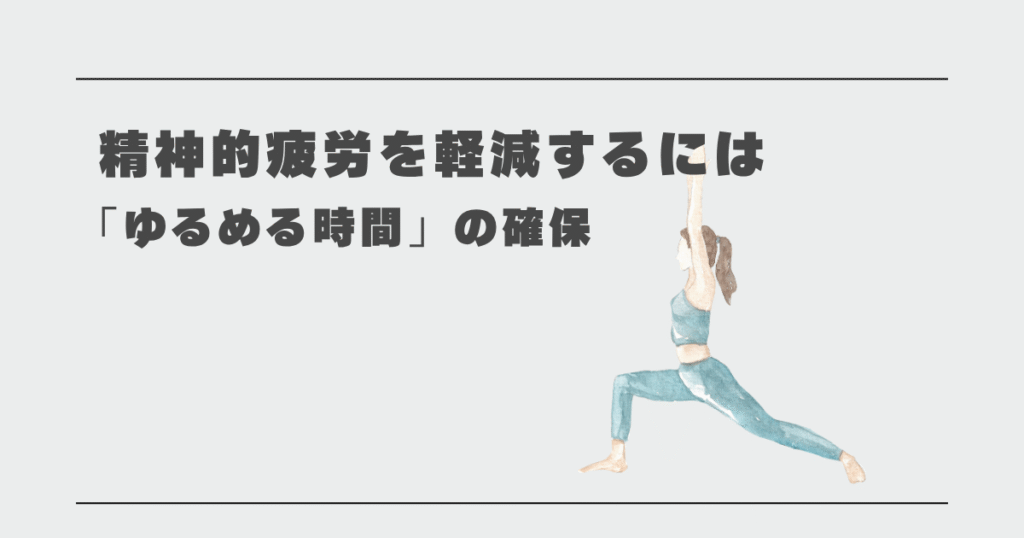
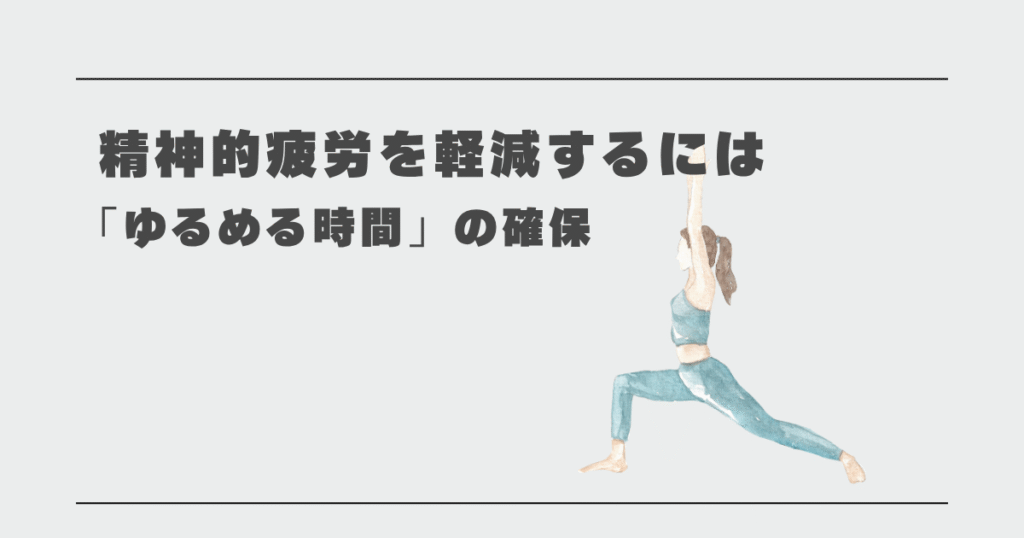
精神的疲労を和らげるには、
- 同じような環境の人と話す
- 週一日は自分の時間を確保する
- 「できたこと」に目を向ける
誰かに話して感情を言葉にする
「話す」ことは心のデトックスです。とくに、ママ友や同僚、SNSコミュニティなどで、共感し合える相手と話すことはストレス解消になります。
話す相手がいない場合は、日記やAIなどを使って書き出し、言語化してみるのもおすすめです。モヤモヤの正体がわかり、スッキリとして気分も軽くなるでしょう。
週一日は自分時間の確保「頑張らない日」をつくる
仕事が休みの日でも、「気がつけば家事や育児に追われて1日が終わってしまう」という人も多いのではないでしょうか。
意識的に、週一日はカフェに行ってゆっくりしたり、趣味のスポーツをしたりするなど、自分時間を確保することも大切です。
ほかにも、外部サービスを利用するなどの工夫をして、「今日は掃除をしない」「今日はごはんを作らない」など、がんばらない日をつくるのもおすすめです。



リセットできる日があるだけで、翌週からの気力も変わってきます
「できたこと」に目を向ける
人は無意識に「足りない部分」を探してしまいます。人間にもともと備わっている向上心ゆえの弊害とも言えます。
しかしながら、疲れているときには「足りないこと」を探すよりも、「できたこと」に目を向けて、自分を鼓舞することの方が心のエネルギーとなります。
夜寝る前には、意識的に「今日できた3つのこと」というテーマについて考えるようにしてみましょう。書き出してみるとより効果的です。
精神的な疲労は、「頑張るためにがんばらない」という意識を持つことが大切です。



限界、と感じる前にほんの少しペースをゆるめる工夫を
環境による構造的疲労は「仕組み」を味方につける
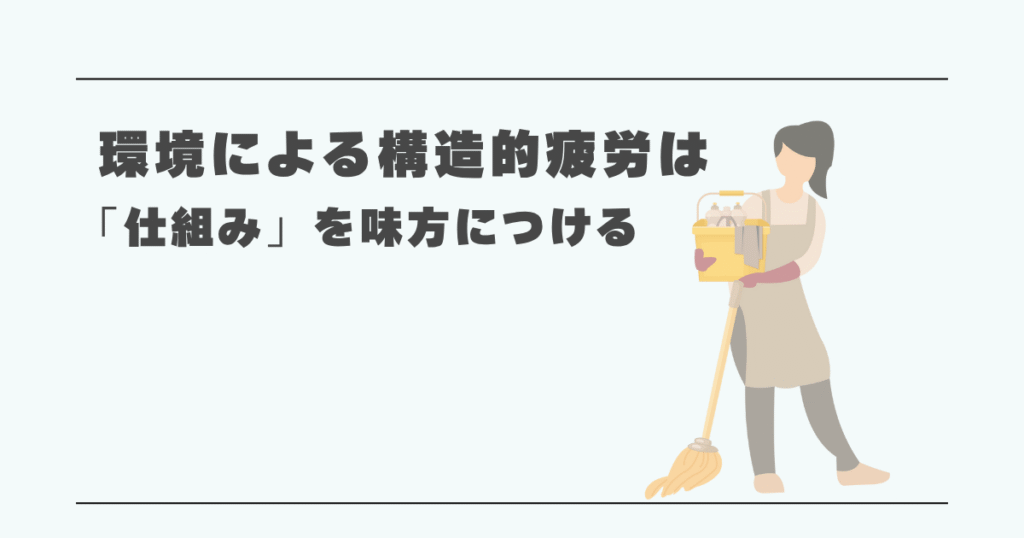
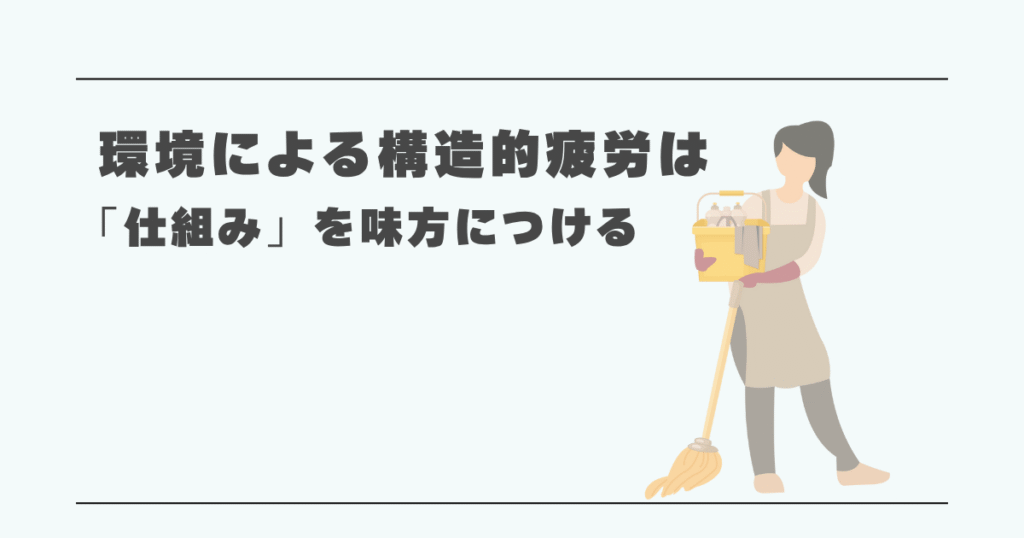
ワーママの疲れは、個人ががんばるだけでは解決できない、家庭や職場環境の「構造的な問題」が根底にあります。
自分だけで頑張ろうとするのではなく、環境や仕組みを変えていくことで解決できることもあります。
具体的には、
- 職場で「働き方」について相談する
- 外の支援を積極的に活用する
- 家族で家事を分担する
など、順番にくわしく紹介します。
職場で「柔軟な働き方」を相談する
職場で「柔軟な働き方」を相談してみるのも環境を変える有効な方法です。
最近では、リモートワークや時短勤務などの制度を取り入れている企業も増えています。
リモートワークや時短勤務は、時間の融通が利きやすくなることで、突発的な事態にも対応しやすくなります。精神的な負担も軽くなるでしょう。
「家庭の事情を相談しにくい」と感じる人もいるかもしれませんが、現在の状況を相談してみることで、解決の糸口がみつかることもあります。
行政支援や外部サービスを積極的に活用
行政の福祉サービスや外部サービスを積極的に活用することも大切です。
たとえば、
- 行政子育てサポート(一時保育、地域子育て支援センター、ファミリーサポートなど)
- 家事代行
- 宅食サービス
- オンライン学習塾、送迎代行
などのサービスがあります。
自分だけでは解決できないことは外部の力を借りて対応しましょう。
家族で家事を分担する
ママがすべてのタスクをこなすのではなく、夫や両親、子供も巻き込んでタスクを分担するようにしましょう。
「金曜日の子供のお迎えはパパにお願い」「土日はおばあちゃんに預かってもらう」「月曜日のゴミ出しは〇〇君の担当」など。
カレンダーアプリ(GoogleカレンダーやTimeTreeなど)を活用しながら、タスクを「見える化」して管理し、「誰が何をいつやるか」を明確にしておきましょう。
長期的に持続できる働き方を目指して、「環境を変える」または「仕組みづくり」をするなどの工夫が大切です。
まとめ
ワーママが限界と感じる疲れる理由は、決して「努力が足りないから」ではありません。
無理を強いられている原因があり、大きく3つに分けられます。
- 時間的疲労
- 精神的疲労
- 環境による疲労
疲れを軽減するために大切なのは、
「完璧を目指さないこと」「人を頼ること」「環境や仕組みを変えてみること」です。そして何より、自分はがんばっていることを認めてあげることが大切です。
ワーママの毎日は時間との戦いの中で、いくつもの仕事をこなしています。



疲れたときには、堂々と「今日は休む日」と言ってください
完璧である必要はありません。ママが笑顔でいることが家庭円満の秘訣だと思います。
参考:介護と仕事の両立はできる?在宅ワークが解決策になる理由【経験者にインタビュー!】